「A級は難しそうで、どこから手をつければいいか分からない…」
そんな方に向けて、この記事では難易度・合格率・勉強時間・科目別対策を、独学で受験した経験をもとにまとめました。
結論から言うと――
- 合格率:平均35%前後
- 受験者数:毎年100名ほど
- 合格者数:30〜40名ほど
- 必要勉強時間:300〜500時間(6か月の計画学習が現実的)
私は 1日2~3時間の学習を6か月ほど続け、独学で初回合格 しました。
A級は“広範囲 × 記述式中心”のため、知識量だけでなく実務的な理解が求められる試験です。そのため、暗記も必要ですが、テキストを「ただ読む」だけでなく、内容を理解して使える状態にし、過去問演習と組み合わせて学習することが欠かせません。
この記事では、A級の 難易度・合格率・勉強時間・合格戦略 を体系的にまとめ、さらに 各科目のポイントやおすすめ教材 まで一気に把握できるよう整理しています。
各科目(貿易実務/英語/マーケティング)の詳しい対策は、以下の記事で解説しています。
▶ A級|貿易実務
▶ A級|英語 (全体対策)
▶ A級 | マーケティング
貿易実務検定A級の難易度は?
A級は、貿易実務検定の中でも最上位の試験であり、記述式中心のため難易度は高めです。
他級との比較(難易度が一目で分かる表)
| 級 | 合格率 | 試験形式 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| C級 | 約60% | マーク式 | 基礎確認レベル |
| B級 | 約50% | マーク式 | 基礎から応用 |
| A級 | 約35% | 記述式中心 | 応用・横断理解が必要 |
受験者数・合格者数の実態
- 受験者数:毎年100名程度(2025年試験は101名)
- 合格者数:30〜40名ほど(2025年試験は32名)
A級は年に1回しか実施されないため、不合格の場合は次回まで1年待つ必要があります。この「受験機会の少なさ」も、A級の難易度を高めている要因のひとつです。
実際に受験して感じた難しさ
本番は会場試験のため、周囲の電卓音や紙をめくる音が気になり、想像以上に緊張しました。「自分だけ遅れているのでは…」と焦った瞬間もあり、精神的なプレッシャーも難易度を上げる要因だと感じました。
貿易実務検定A級の合格点の目安
合格ラインは公表されていませんが、C級は80%、B級は70%です。A級は他の級と違って記述式が多いため、合格ラインは低めになると思います。また、実際に受験した経験から、おおよそ60%前後ではないかと考えています。
私は自己採点で65〜70%を取ることができ、無事合格できました。合計で300点(約65%)を取れれば、合格は十分現実的だと思います。
| 科目 | 配点 |
|---|---|
| 貿易実務 | 200点 |
| 英語 | 150点 |
| マーケティング | 100点 |
| 合計 | 450点 |
特に英語は配点が150点と大きいため、得意な方は有利に進められるでしょう。
通関士試験との違い
A級と通関士の違い(比較表)
両試験は一部重なる部分もありますが、出題範囲や求められる知識の深さは大きく異なります。通関士試験は、輸出入通関に関する法令や計算をより深く問う国家資格です。
| 項目 | A級 | 通関士 |
|---|---|---|
| 出題範囲 | 貿易実務全般 | 法令中心(関税法・通関業法・外為法など) |
| 英語 | あり | ほぼなし(インボイスは英語表記) |
| マーケティング | あり | なし |
| 計算 | あり | 多い |
| 性格 | 貿易実務総合型 | 国家資格 |
実際に両方を受験した感想
私は商社で貿易実務を経験しており、英語が得意科目です。一方で、通関業者での経験はありません。そのため、英語科目がなく、通関業務の知識を深く問われる通関士試験の方が難しく感じました。
通関士試験の平均合格率は約15%前後で、合格するための目安は各教科およそ60%程度です。A級と同程度の得点率が必要ですが、合格率はA級より低めに出ています。
私はA級合格後に通関士試験の勉強を始め、約10カ月かけて挑戦しました。自己採点では、通関業法・関税法等・通関実務の各教科で75%以上を獲得し、A級よりも高得点で合格できましたが、勉強期間はA級より長くなりました。
貿易実務検定A級の勉強時間と進め方
C級、B級に合格してから数年が経ち、次はA級にも挑戦してみようと思いました。
独学の場合、必要な勉強時間は 300〜500時間。期間にすると 6か月 が現実的だと思います。
- 1〜2か月目公式テキスト(貿易実務ハンドブック アドバンス版)精読+用語整理
- ただ読むだけでなく、内容を理解して使える状態にする
- テキストのチェック問題も解きながら理解できない箇所を無くす
- 3〜4か月目過去問演習(まずは過去問に慣れることを意識)
- まずは時間を気にせず、解き方の型をつかむ
- 解説を読み込み、知識を実務に結びつける
- 5か月目過去問演習(時間配分も意識)+弱点補強
- 過去問を一通り解き終えて2周目に入る頃からは、“本番を意識したスピード”が重要
- 苦手分野も捨て科目にせずに学習し点数の底上げを図る
- 6か月目過去問演習(本番と同じ時間配分でトライ)
- 仕上げは「時間内に終了できる練習」
- 自分なりの時間配分を意識
私はこの流れで 初回合格できました。過去5年間の過去問を 3回繰り返し 解き、5か月目以降は必ず時間を計って取り組みました。
丁寧に解くことも大切ですが、実務ではスピード感も求められます。A級でも同じで、「正確さ × スピード」 の両方が必要だと感じました。
実際に私が使用したテキストや参考書は、記事の最後で紹介していますので、これから勉強を始める方はぜひ参考にしてください。
貿易実務検定A級に合格するコツ
①:「苦手科目の底上げ」
得意科目だけで勝負するのはリスクがあります。試験本番では緊張から思わぬミスも起こりがちです。そのため、得意科目での失点をカバーできるよう、苦手科目の底上げをしておくことが大切です。
私自身、比較的得意としていた海上運賃計算の問題で、アメリカの都市の位置関係を誤り、計算手順は合っていたのに答えを間違え大きく失点しました。
その代わり、苦手科目だったマーケティングを一通り勉強し、基本問題を確実に解けるようにしていたため、この失点をカバーできました。マーケティングは過去問を解いても最初は30%しか取れませんでしたが、基礎を固めて50%まで上げることができました。
また、英語は得意でしたが、法律英語のように苦手な分野もありました。そうした部分も放置せずに勉強することで、科目全体の理解が深まり、得点につながります。
②:「過去問を解く」
ブログ前半でも書きましたが、まずはA級の公式テキストをじっくり読み込み、その後は過去問を繰り返し解いて理解を深める方法が効果的でした。
A級では、過去問と似た形式の問題が繰り返し出題される傾向があります。私は過去5年間の過去問を3回繰り返し解きました。少なくとも3年分の過去問にトライすることをおすすめします。
過去問は、マウンハーフジャパンで販売されています。A級は1回分が税込4,158円と高額ですが、出題傾向の把握や時間配分の練習に役立ちます。
過去問は「解く → 解説を読む → テキストに戻る」のサイクルを回すことで、理解が一気に深まります。
各教科のポイント
ここではざっくりとしたポイントをまとめます。詳細は各科目の記事で解説しています。
貿易実務
貿易実務分野では、特にL/Cや書類作成と運賃・関税計算への対策が大切です。基本を確実に押さえ、過去問で実践力を身につけることが、合格への近道です。
- 信用状(L/C)取引の理解
仕組み・用語・実務の流れをしっかり押さえておくことが大切です。 - 書類作成力
輸出入書類はある程度パターン化されているため、過去問を繰り返し解くことで、書類作成の力が着実につきます。 - 運賃・関税計算で問われる基礎知識
海上・航空運賃は毎回出題されます。計算方法に加え、アメリカの主要都市の位置関係や端数処理は知らないと失点してしまうケースがあるため、確実に押さえておきたい部分です。関税計算も基礎ルールの理解が必要です。 - 国際税制の基礎知識
難しく見えても基本問題が中心。得点源になりやすい分野です。
▶ A級|貿易実務
英語
英語分野では、契約・保険に関する表現、インコタームズの正確な理解、大きな桁の数字感覚が押さえておきたい重要項目です。
- 契約や貨物海上保険に関わる法律用語
例:effect 「(保険を) 付保する」、in good faith 「誠意をもって」など - インコタームズの正確な英語名と日本語名
例:CIP=輸送費保険料込み(※「運賃保険料込み」は誤り) - 大きな桁の数字の感覚
例:「$3.6 billion」=「36億円」など、数字の感覚も重要です。
マーケティング
マーケティング分野では、基本用語の暗記と計算問題への対応が得点アップのカギです。過去問で出題傾向を確認し、知らない用語は検索して調べ、理解を深めました。
- マーケティング用語とその定義:
SWOT分析、3C分析、PEST分析、プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント (PPM)、ブルーオーシャン戦略など。内容は基本的なものが多く、どれだけ用語を覚えているかが得点のカギになります。 - 計算問題:
損益分岐点売上高、GMROI(商品投下資本利益率)、交差比率の計算方法が複数回出題されています。最初は難しく感じるかもしれませんが、計算式を覚えてしまえば、問題4(計算問題)にも十分対応可能です。GMROIや交差比率は理解しづらいと感じる方も多いと思います。私自身は正直、理解できているとは言えませんが、計算式だけはしっかり覚えておいたおかげで、問題には対応できました。理解することがベストですが、試験対策としては「まずは暗記」も十分に有効な戦略だと思います。
おすすめ参考書・教材紹介
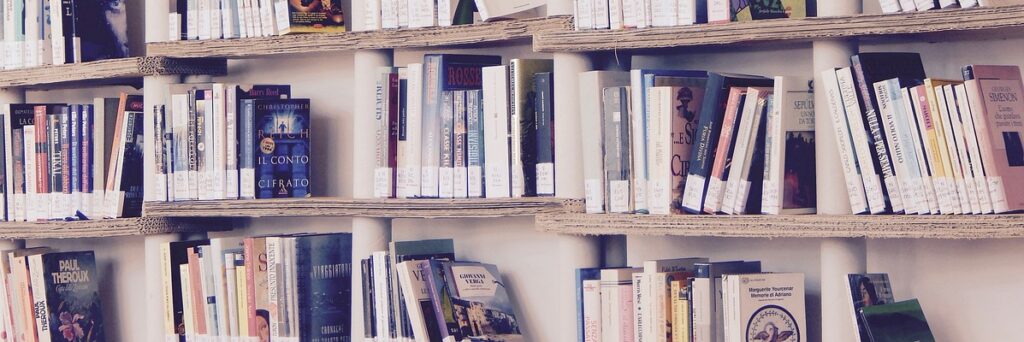
貿易実務検定A級の学習の際に実際に使用した教材で、おすすめ教材一覧 をまとめました。効率的な勉強の参考になれば嬉しいです。
- 貿易実務ハンドブック ベーシック版
C級向けですが、アドバンス版で理解が難しい箇所の補強に最適です。特に外為法の「輸出許可・承認が必要な貨物」「輸入承認が必要な貨物」が具体的に分かりやすく解説されています。 - 貿易実務ハンドブック アドバンス版
A級・B級どちらにも役立つ基本テキスト。章ごとにチェック問題があり、理解を確認しながら進められます。。ただ、A級の出題範囲を完全にはカバーしていないため、過去問を解きながら問われている分野を把握し補完が必要です。特恵関税制度、経済連携協定(EPA)の仕組みについてはテキストを基本として、それ以上の深い理解が必要になります。国際税制に関する基本用語も補強が必要です。またマーケティングに関しては扱っている内容が少ないため、より幅広いマーケティングの基礎知識を身に着ける必要があります。テキストで足りない部分はインターネットで検索して補強しました。 - 通関士合格の基礎知識
通関士試験用ですが、関税計算や実務問題の理解に役立ちます。貿易実務ハンドブックとは別の角度から説明されているため、理解が曖昧だった部分が腑に落ちることもありました。
最後に
貿易実務検定A級は難関ですが、苦手分野の底上げ × 過去問演習 × 計画的な学習の3つを徹底すれば、独学でも十分に合格可能です。焦らず、着実に学習していきましょう。
貿易実務検定A級 関連記事一覧
A級の科目別の具体的な対策も順を追ってご紹介していますので、参考にしていただければと思います。
▼ 全体像・ロードマップ
・A級|概要(※本記事)
▼ 科目別対策
・A級|貿易実務
・A級|英語 (全体対策)
・A級|英語:頻出単語(法律・海上保険)
・A級|英語:インコタームズ
・A級|英語:大きな数字の読み方
・A級|マーケティング


